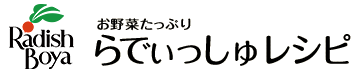大豆から油揚げになるまでの道のりでは、様々な大豆製品ができています。
栄養たっぷりの大豆はたくさん摂りたいものですが、乾燥させたままでは消化がしづらい。
そこで先人たちが知恵を絞って、日本独自の大豆文化を今に伝えています。手作りの油揚げで、そのエッセンスを感じてみましょう。
油揚げの作り方
 ボウルに大豆を煎れ、1.2Lの水にひと晩浸します。芯がなく、指で押すとつぶれるくらいにふっくらと膨らみます。 ボウルに大豆を煎れ、1.2Lの水にひと晩浸します。芯がなく、指で押すとつぶれるくらいにふっくらと膨らみます。 |
 充分柔らかくなった大豆を1/3ずつに分けて、ミキサーにかけます。豆の強い香りがする、どろりとした「生呉(なまご)」と呼ばれる液体になります。 充分柔らかくなった大豆を1/3ずつに分けて、ミキサーにかけます。豆の強い香りがする、どろりとした「生呉(なまご)」と呼ばれる液体になります。 |
 深い鍋に1.6Lのお湯を沸かし、生呉(なまご)を入れます。鍋底が焦げつかないようヘラで混ぜながら加熱し、沸騰させます。 深い鍋に1.6Lのお湯を沸かし、生呉(なまご)を入れます。鍋底が焦げつかないようヘラで混ぜながら加熱し、沸騰させます。 |
 泡がもこもこと吹き上がります。一旦沸騰させたら火を止め、泡が収まったら再び火をつけて混ぜながら10分ほど煮込みます。火が通るとこっくりとした大豆の甘い香りが漂い、泡も小さく繊細になってきます。 泡がもこもこと吹き上がります。一旦沸騰させたら火を止め、泡が収まったら再び火をつけて混ぜながら10分ほど煮込みます。火が通るとこっくりとした大豆の甘い香りが漂い、泡も小さく繊細になってきます。 |
 ボウルにザルを重ね、こち袋に鍋の中身を入れます。箸やヘラを使い、熱いうちに絞ります。やけどに注意。 ボウルにザルを重ね、こち袋に鍋の中身を入れます。箸やヘラを使い、熱いうちに絞ります。やけどに注意。
ここで出来たのは… ■豆乳 ■おから |
 豆乳を70~75℃に温める。にがりをぬるま湯(50cc)に加えて溶かし、ヘラなどにたらしながら手早く加え、全体を数回かき混ぜます。 豆乳を70~75℃に温める。にがりをぬるま湯(50cc)に加えて溶かし、ヘラなどにたらしながら手早く加え、全体を数回かき混ぜます。 |
 10~15分そっとしておくと、全体が固まってふわっとした豆腐を透き通った液体に分離します。 10~15分そっとしておくと、全体が固まってふわっとした豆腐を透き通った液体に分離します。 |
 モロモロの状態になったら型にさらし布をしき、すくって型に入れます。蓋をして軽く重しをし、15分ほど水を切ります。 モロモロの状態になったら型にさらし布をしき、すくって型に入れます。蓋をして軽く重しをし、15分ほど水を切ります。 |
 水にさらし、余分なにがりを抜きます。 水にさらし、余分なにがりを抜きます。
ここで出来たのは… ■豆腐 |
 出来上がった豆腐を1cm程度の薄切りにし、重しをして1~2時間ほどしっかり水切りをします。 出来上がった豆腐を1cm程度の薄切りにし、重しをして1~2時間ほどしっかり水切りをします。 |
 よく水が切れ、全体が薄くなったら130℃程度の低温の油で揚げ、さらに180℃の高温の油で2度揚げする。 よく水が切れ、全体が薄くなったら130℃程度の低温の油で揚げ、さらに180℃の高温の油で2度揚げする。 |
 じゅわっと揚がった、出来たての油揚げは、なんともカリッと香ばしい。 じゅわっと揚がった、出来たての油揚げは、なんともカリッと香ばしい。 |